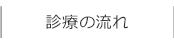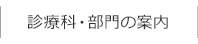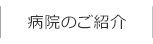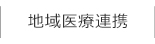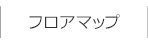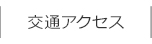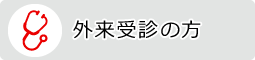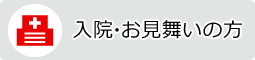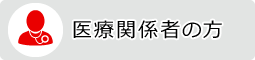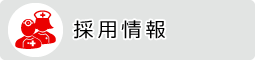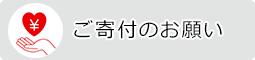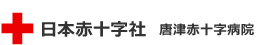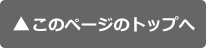当院の輸血に係る方針
「輸血後の感染症検査のご案内」をお渡しした患者さんへ
このご案内は、輸血後感染症検査に関する直近の指針と、それに伴う当院での対応の変更点についてお伝えすることを目的としています。
背景
2004年に改正された「輸血療法の実施に関する指針」に基づき、これまで輸血後感染症検査(HBV、HCV、HIV)が推奨されてきました。しかし、2014年に輸血用血液に対する個別NAT検査が導入されたことにより、輸血後の感染症は大幅に減少しました。日本国内において、2015年からの過去5年間の調査では、輸血後のHBV感染が3例報告されたのみで、HCV、HIV感染は報告されていません。
日本細胞輸血治療学会の見解
これらの状況を踏まえて、日本輸血細胞治療学会は以下の見解を示しました。
- HBV、HCV、HIV 輸血後感染症検査は、従来から感染が疑われる場合に実施する検査とされており、患者の負担、医療者の負担、費用対効果の面から考えても、輸血された患者全例に実施すべき検査ではない。
- 輸血によってHBVに感染した3名の患者の基礎疾患は、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫であったことから、病原体の感染が患者に大きな影響をもたらす場合(基礎疾患や治療で免疫抑制状態の患者や輸血後感染症になった場合に治療法が限定・変更される可能性がある患者)に担当医の判断で輸血後感染症検査を実施しても良い。
-
輸血前検体保管は全例で実施すべきである。
-
輸血後感染症検査の実施率を病院の機能に対する外部機能評価に用いない。
当院の対応
上記の日本輸血細胞治療学会の通達を受け、当院では以下のように対応を変更します。
- 輸血同意取得時の輸血後感染症検査案内の配布を取りやめます。
- 輸血後感染症検査は担当医の判断で実施する以外は推奨いたしません。
宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応について
相対的無輸血
当院では、患者様との信頼関係を第一に考えて、十分な説明と同意の上で医療行為を行なっており、出血の可能性のある治療では、平素より極力輸血せずに済むように心がけております。
しかし、治療の経過によりましては、患者様の全身状態の維持・改善のため、必要最低限の輸血が必要と判断される場合があり、出血性ショックなど、「生命の危機」の状態で救急搬送を要請される患者様に直面する事もあります。
患者様のなかには、宗教的信条で、一切の輸血を拒否される方々がいらっしゃいます(「絶対的無輸血治療」※1のご希望)。こうした場合でも、私たちは、医師の倫理に基づき輸血を実施する立場をとっております。私たちは、以下の基本方針に則り、輸血を拒否される患者様について対応させていただきますので、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
基本方針
- 当院では、いかなる場合においても「相対的無輸血治療」※2 の立場をとります。
- 「絶対的無輸血治療」※1に関連した免責証明書等をお持ちいただいた場合においても、当院は「相対的無輸血治療」※2の方針をとらせていただきます。
- 相対的無輸血治療に同意いただけるように努めますが、最終的に同意が得られない場合は、他院での治療をお勧めします。
- 出血性ショック等による瀕死の病態で、輸血以外に救命の手段がないと判断される緊急の場合は、輸血同意書が得られない場合でも救命のための輸血療法を実施いたします。
※1【絶対的無輸血】
患者様の意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
※2【相対的無輸血】
患者様の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方。