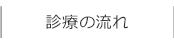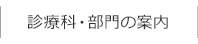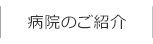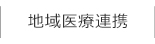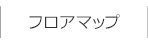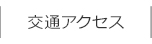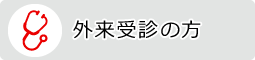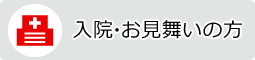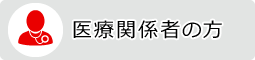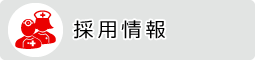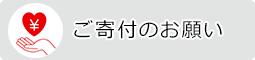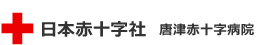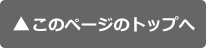薬剤部
病院長交代に伴うご案内
当院では2022年4月1日付で病院長交代を行いました。
これに伴うご案内について、詳細はこちらをご確認ください。
薬剤部の紹介
薬剤部では『安全・安心』を基本理念とし、病院内で取り扱う全ての医薬品について、患者さんに正しく安全にご使用いただけるよう、様々な業務を行っています。特に、大きな柱として5つの目標を掲げ、医療チームの一員として思いやりの心をもち、薬学的な専門知識に基づいた視点から医療の質と患者さんのQOL(生活の質)の向上に貢献し、安全で適切な薬物療法を提供できるよう薬剤部一同努力しております。
目標
- 調剤過誤防止とセーフティマネージメント
- 医薬品安全性情報報告とプレアボイド
- コスト意識の確立と後発医薬品への対応
- 専門薬剤師養成と薬剤師教育への協力
- 治験業務の確立
薬剤部の組織 (令和7年8月25日現在)
薬剤助手 3名
連絡先・お問い合わせ
電話:0955-72-5111(代表)
ファックス:0955-58-8117(薬剤部内直通)
業務の紹介
業務紹介動画
調剤業務

薬剤部内の調剤業務は、終日稼働の院内電子カルテシステムからの情報を、薬剤部門管理システムに取り込み、安全性を確保するとともに細心の注意を払って調剤をしています。このとき、医薬品の取り間違いのないよう、監査システムを利用しています。また調剤された薬は、別の薬剤師が再度チェックし、患者さんや病院内の他の医療スタッフが安心して使用できるよう努めています。
内服・外用薬調剤
入院患者さんのお薬と外来患者さんの一部のお薬を、医師の処方せんをもとに調剤しています。また調剤の際には、薬の専門家としての知識を生かし、他の診療科から出されているお薬との重複や用法・用量、相互作用等を確認し、患者さんが安心してお薬を使用していただけるようにしています。


注射薬調剤
入院患者さんに使用する注射を、医師の処方せんをもとに各病棟に供給しています。また調剤の際には、注射薬の組み合わせや用法・用量等を確認しています。なお安全性を高めるため、毎日患者さんごとに1日(1回)分をセットするとともに、添付するバーコード付き専用ラベルにより、各病棟では施行時のバーコード照合機能を活用しています。

製剤業務
製剤業務としては、院内製剤(市販されていない薬や消毒薬等)の調製と注射薬の混合(ミキシング)調製を行っています。注射薬のミキシングは、専用のキャビネットにて個々の患者さんの高カロリー輸液や抗がん剤等の無菌調製を行っています。なおこの時、無菌的に注射薬を混合するだけでなく、用法・用量・配合変化等を含めた処方内容のチェックを行い、安全な薬剤として患者さんに投与できるようにしています。


薬品管理業務
病院内で使用する全ての医薬品の購入、品質ならびに数量の管理を行い、患者さまに安心して使用していただけるようにしています。また麻薬・毒薬・向精神薬等、厳重な管理が必要な医薬品については、慎重な管理のもと、安全性に対応しています。特に薬品棚においては効能別、ハイリスク薬等、より厳密な分類分けを施し、医療安全を主眼においた管理を行っています。



薬品情報管理業務





薬剤管理指導業務・病棟薬剤業務
薬剤部では、各病棟担当薬剤師を配属し、入院患者さんの入院時初回面談や服薬指導、退院時の服薬指導のほか、医師や看護師への情報提供等を行っています。特に入院患者さんについては、ベッドサイドで薬の使い方や薬効(薬の効果)等を説明し、薬歴管理としては、患者さんが使用中のお薬全般(内服・外用・注射薬)を通じて、副作用や相互作用、お薬の重複等、多種多用な背景のもと、薬物療法の手助けをしています。さらに、患者さんの服薬歴(以前服用していたお薬の記録)や副作用歴、症状等をより的確に把握し、適正な薬物療法の推進に努めています。


各種医療チーム参加
糖尿病教室
薬剤部では、医療社会事業課が主催する糖尿病教室に対し、日本糖尿病学会他、計3学会が認定する薬剤師(日本糖尿病療養指導士)を派遣し、院内・院外からの糖尿病患者さんや家族のための講義を定期的に行っています。糖尿病教室では他に、医師、管理栄養士、理学療法士、看護師等がそれぞれの専門分野で講義を行い、薬剤師は主に、薬物療法に対して幅広い専門知識を生かし、経口糖尿病薬やインスリン自己注射等、患者さんに薬物療法への十分な理解をいただけるように努めています。
感染制御チーム(ICT)
薬剤部では、『ICT』のメンバーとして、担当薬剤師が同行し、定期的に院内ラウンドを行っています。このラウンドは、専門医師、看護師、検査技師とともに、院内各科・病棟での感染症発生状況・環境汚染状況・保菌者や細菌検出状況・感染予防対策状況・抗菌薬使用状況等の把握を通じて、感染防止に関する教育指導、感染対策・予防措置の助言や提案、感染症アウトブレイク発生時の調査や対応を目的としています。薬剤師はその中で、消毒法や薬物療法等に関し、必要に応じた助言を行うよう努めています。
緩和ケアチーム
薬剤部では、『緩和ケアチーム』のメンバーとして、担当薬剤師が同行し、定期的に院内ラウンドを行っています。このラウンドは痛み等、からだの症状を緩和する医師、気分の落ち込み等、心の症状を緩和する精神科の医師、緩和ケアを担当する看護師、食事の工夫相談を担当する管理栄養士、生活や経済的な問題について相談を受けるソーシャルワーカーとともに、院内各病棟でのがんの痛みに苦しんでおられる患者さんの状況を把握し、必要に応じた主治医への助言を行い、患者さんが抱えている問題を解決することを目的としています。薬剤師はその中で、医療用麻薬をはじめとする心や体の痛みを緩和するお薬に関して、助言や情報提供をしています。
がん薬物療法
がん薬物療法には多くの種類の薬を使用することが多く、治療の目的、効能効果、副作用、至適投与量の検討などについて、薬剤師の観点は必要不可欠です。医師、看護師などの他職種スタッフと協力し合いながら、チームが一体となって患者さんのがんの治癒を目指しています。その中で薬剤師は、(1)患者さん個々の理解度とニーズを考慮したお薬の効果、副作用発現のタイミングや初期症状などについての服薬指導、(2)薬剤師間で情報を共有したり、他の医療スタッフに対する薬剤情報の提供をしたりする情報の共有化、(3)がんの種類やステージに応じた標準治療、投与スケジュールなどの知識を習得しながら行うレジメンの作成・管理、(4)投与計画のチェックや薬歴管理、支持療法(副作用の予防・治療)の薬剤選択への対応などの安全管理、(5)抗がん剤の調製・監査、など、多くの役割を担っています。
栄養サポートチーム(NST)、褥瘡
原則として全ての入院患者さんを対象に栄養評価を行い、適切な栄養療法が安全に施行できる環境を構築し、栄養障害や褥瘡(いわゆる床ずれ)を予防・治療すること、また病院スタッフの栄養管理及び褥瘡に対する認識を高めることを目的として活動しています。医師、薬剤師、看護師、栄養士など多くの職種からなる栄養サポートチーム(NST)は、すべての治療の根幹となる栄養療法を担っており、栄養障害を抱える患者さんに対してはNSTカンファレンス・回診を、褥瘡患者さんに対しては褥瘡回診を実施しています。この中で薬剤師は、(1)薬学的知識に基づいた栄養療法の提言や問題点の抽出、(2)処方提案やモニタリング、(3)栄養剤や医薬品の説明、(4)医療スタッフへの各種情報提供などを行っています。
薬学生実務実習・新人教育・資格取得
薬学生実務実習
薬学部5年生が行う11週間の実務実習を受け入れています。コアカリキュラムに沿ったテキストを参考に進め、当院の業務に沿ったスケジュールを組んで指導しています。薬剤部内の業務としては調剤実習のほか無菌調製の実習も充実させており、また、他部署の協力のもと、病棟業務の見学や体験、他部署(栄養課、検査課、放射線課、リハビリテーション等)の見学を行っています。
新人教育
1週間の全体研修を終えた新人薬剤師には、日々の薬剤師業務を覚えてもらうために、数年目の先輩薬剤師が指導薬剤師となりコーチングしていきます。3~4ヶ月の研修期間で、当直業務を行えるようになることを第一目標に設定しています。研修期間中は、新人薬剤師研修プログラム(兼新人薬剤師業務マニュアル)を使用して日々の業務に励んでもらい、病棟業務への配属に備えます。
資格取得
資格取得のため、各種学会や研修会に参加をしています。また、月1回薬剤部カンファレンスを行い、業務内容の改善や、症例報告を通して知識の向上を目指しています。
当院薬剤師の資格取得状況(令和7年8月現在)
- 日本薬剤師研修センター 認定薬剤師
- 日病薬病院薬学認定薬剤師
- 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師
- 糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士資格取得薬剤師
- 日本静脈経腸栄養学会 栄養サポートチーム(NST)専門療法士
- 日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師
- 日本病院薬剤師会 日病薬認定指導薬剤師
- 日本アンチ・ドーピング機構(JADA) スポーツファーマシスト
- 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師
患者さんへ
院外処方せんについて
厚生労働省がすすめる医薬分業の方針に基づき、1997年9月から、院外処方せんを発行しています。ご理解とご協力をお願いします。『処方せん受付』『保険薬局』『基準薬局』『保険調剤』等の表示があれば、どの保険薬局(調剤薬局)でも院外処方せんによりお薬を受け取ることができます。
医薬分業とは?
院外処方せんファックス送信サービス
お薬の受け取りを希望される保険薬局をあらかじめ指定し、処方内容をあらかじめファックスで送信することができます。送信することで、受け取りを希望される保険薬局において、あらかじめ調剤をしていただき、保険薬局では少ない待ち時間でお薬を受け取ることができます。待ち時間短縮のためにも、ファックス送信をお勧めします。なお会計窓口向かい側(13番)に無料ファックスが設置してあります。ご利用ください。



保険薬局(調剤薬局)でお薬を受け取るまでの流れ
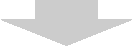
使用方法がわからない場合は、常駐する佐賀県薬剤師会職員が説明します。
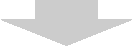
※病院が休みで救急外来に受診され、院外処方せんの交付を受けられた患者さまは、 病院が休みの場合、無料ファックスが利用できません。その場合 は直接、処方せんを保険薬局へお持ち下さい。ただし当院では、患者さんの『かかりつけ薬局』の営業状況が不明ですので、休日のお薬お受け取りを、病院横の『唐津・東松浦薬剤師会薬局』に、原則として指定させていただいております。ご了承下さい。
院外処方せんに印字される”臨床検査値”について
おくすりを安全に使用するためには、適切な用法用量での使用や副作用の早期発見が重要となります。検査値が印字された院外処方箋を調剤薬局にご提出いただくことによって、調剤薬局でも様々なチェックが可能となり、副作用の防止など、より安全な医療の提供に繋がるものと考えております。なお、記載される検査項目、基準値など詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
みなさまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※臨床検査値の印字を希望されない場合は、診察時に医師までご相談ください。
※基準値や単位については検査方法の変更等により改訂されることがありますので、掲載情報の更新にはご注意いただくよう、お願いいたします。
院外処方に関するご質問例
処方せんって何ですか?
医師や歯科医師は、診察すると患者さんの病気の治療に使用する薬の種類、量などを決めます。これを記載したものが処方せんです。
お医者さんは、どうしてお薬をくれないで、処方せんをくれるのですか?
医師や歯科医師は、処方せんを出すことにより、薬の管理等の業務を薬剤師に任せることができ、その分、診察に時間をかけることができます。
処方せんをもらったら、どうしたらいいのですか?
『処方せん受付』『保険薬局』『基準薬局』『保険調剤』等の表示のある薬局であれば、全国どこでも調剤してもらえます。お好きな薬局へお持ち下さい。ただし発行された処方せんの有効期限は、通常、発行日を含めて4日間ですので注意して下さい。
『かかりつけ薬局』とは?
患者さんが、常に利用する調剤薬局のことをいいます。かかりつけ薬局をもつ利点は、どこの病院・診療所にかかっても、処方せんを持っていく調剤薬局を一つに決めておくことで、重複投与や相互作用の防止と患者さんの一元的な薬歴管理等を行ってもらえることにあります。
調剤薬局では、お薬のことを何でも聞けるのですか?
調剤薬局では、お薬を安心して使っていただくために、使用方法や保管方法等の説明を十分に聞くことができます。また、市販薬との飲み合わせ、健康食品との飲み合わせ等、多種多様な質問にも薬剤師がお答えします。
『薬歴』って何ですか?
調剤薬局では、患者さんの体質やお薬のアレルギー歴、どんな薬をいつ頃使用したか、患者さんへの指導内容等、患者さんの情報を詳細に記録します。これらの記録を『薬歴』といい、薬剤師が調剤する上での貴重な情報となります。
調剤する前にいろいろ聞かれることがあるが、何故でしょうか?
調剤薬局では、患者さんからの多種多様な情報により、アレルギーや副作用の心配がないかなど、いろいろチェックしています。これら収集された多くの情報は、薬歴と一緒に厳重に保管されています。お薬の適正な指導をしてもらうためにも、情報を正確に伝えましょう。
処方せんは代理人が持っていっても良いのですか?
処方せんがあれば、ご本人でなくても構いません。患者さん自身はお宅でお休みになり、ご家族等が処方せんをお持ちになっても、調剤してもらえます。
処方せんがなくても、以前調剤してもらったお薬をもらえるのでしょうか?
いいえ。処方せんは1回限りで、そこに書かれた数量だけしか調剤できません。再度お薬が必要な場合は、その都度、病院・診療所等で診察を受けるなどし、再度処方せんをもらって下さい。
処方せん調剤の料金は、調剤薬局によって違うのですか?
保険処方による調剤の料金は、調剤薬局によって若干異なる場合があります。特に、自己負担のある患者さんの場合、若干費用が高くなる場合がありますので、ご承知おきください。
ジェネリック(後発)医薬品とは?
販売特許が切れた医薬品に対し、他の製薬会社が発売する『同成分』『同規格』等のお薬をいい、厚生労働省が設定するお薬の値段(薬価)も、安価なものに設定されています。
ジェネリック(後発)医薬品を処方してもらうには?
ジェネリック医薬品は、主治医の判断で処方してもらえます。ただし、同じ成分や含量にも関わらず、お薬の形状や製薬会社間によっては、若干の効能や治療効果の相違等が存在する場合があるようです。まずは主治医にご相談下さい。
必要なお薬をもらうのを忘れたのですが、どうしたらよいでしょうか?
調剤薬局でお薬をもらう時、必要な薬が処方されていなかった場合は、調剤していただく薬局にてご相談下さい。薬剤師が直接、処方医に連絡を取り対応します。なおその他、処方のお薬の件で、処方医に訪ねたいことがある場合にも、薬剤師にお申し付け下さい。ただし、問い合わせに若干のお時間を要する場合がありますので、ご了承下さい。
処方せんを紛失したのですが、どうすればよいのですか?
処方せん紛失の場合、処方医に相談して、処方せんの再発行ができます。ただしその場合、患者さんか家族の方等が、直接ご来院いただくことになります。なお、処方せん再発行手数料が自費で発生しますので、紛失されませんようくれぐれもご注意下さい。
医療関係者の方へ
調剤薬局へのお知らせ
院外処方せんに印字される”臨床検査値”について
2018年1月20日より、当院では、患者さんの臨床検査値の一部を院外処方せんに印字することとしました。検査が実施されていない項目は空欄表示となります。また、記載される検査項目、基準値など詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
臨床検査値をご活用いただくことで、薬物療法の安全性向上・地域連携の充実に繋がるものと考えます。みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
院外処方箋上に印字される検査項目
※基準値や単位については検査方法の変更等により改訂されることがありますので、掲載情報の更新にはご注意いただくよう、お願いいたします。
調剤事故発生時の対応
調剤事故を含むミスが発覚した場合は、直ちに薬剤部まで連絡をし、指示を仰いで下さい。
院外処方せん疑義照会
処方内容等の確認は処方医に対し、直接電話で問い合わせを行って下さい。
保険番号等の確認
医事課に対し、直接電話で問い合わせを行って下さい。
調剤方法等の確認
薬剤部に対し、直接電話で問い合わせを行って下さい。
疑義照会報告書
処方せん右側の『報告書』に詳細事項を記載し、ファックスで送信して下さい。
ファックス送信等に関する問い合わせ
院外処方ファックスコーナーに対し、直接電話で問い合わせを行って下さい。
※受け付けた処方せんの記載内容で、医薬品名称に『手書き』が存在した場合、早急に薬剤部までお知らせ下さい。確認の上、次回処方時にできるだけ処方できるように、電子カルテシステムへの名称登録を行う予定です。
採用医薬品について
当院薬事審議会における採用医薬品状況についてお知らせします。
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2025年12月)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2025年10月)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2025年8月)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2025年6月)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2025年4月)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2024年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2023年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2022年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2021年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2020年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2019年度)
- 唐津赤十字病院採用薬情報(2018年度)
がん薬物療法レジメンについて
当院では現在、大腸がん、胃がん、乳がん、肺がん、血液がんなどに対する約300種類のレジメンを登録しております。
当ホームページで公開するレジメンは、唐津赤十字病院のがん化学療法委員会で審査され、院内レジメンとして承認されたものについて、その内容を保険薬局薬剤師などが利用するためのものです。当院でがん治療を受ける患者の適正な投与管理を目的として提供されるものであり、その他の目的での用途は想定しておりません。投与量、投与スケジュール、前処置薬等は、患者さんの状態によって変更される場合があります。また病名として該当する患者さんすべてに治療の適応とはならないことをご了承ください。
掲載内容については、無断転用を禁じます。
掲載内容は随時追加・更新予定です。
唐津赤十字病院 薬剤部 医薬品情報管理室
各種申請手続きについて
1.当院へ出入りされる企業の皆様へ
当院薬剤部ではお取引業者様管理・アポイント予約システム(MONITARO Lite)を導入しています。皆様のご連絡先等の情報管理や面会アポイント申請とスケジュール調整を、本システムを介して行い、互いの業務効率化を推進したいと考えております。
MONITAROへのご登録のない方については、面会申請をお受けいたしかねる場合もございますので、お忙しい中恐縮ですが、下記「MONITARO Lite手順書」をご覧になり、内容に従って登録をお願いいたします。
併せて、「面会予約申請時のお願い」もご覧いただきますようお願いいたします。
書式・様式ダウンロード
2.医薬品等の製品販売後調査の依頼について
製造販売後調査(使用成績調査、特定使用成績調査、副作用・感染症報告等)を新規に申し込む場合には、まず当該調査責任医師・担当医師と話し合いの上、合意が取れましたら下記「医薬品等の製品販売後調査実施マニュアル(依頼者用)」を参考に必要書類を作成・準備し、薬剤課長までご提出ください。
契約変更時、支払い時、終了時に関しても、下記「医薬品等の製品販売後調査実施マニュアル(依頼者用)」をご参照ください。
注意
- ご訪問の際は必ず事前にアポイントをお願いします。
- 製造販売後調査は、当院で採用(仮採用、臨時採用含む)されている医薬品及び医療機器が対象です。
- 採用前には申請を受理いたしかねますので、採用後にご申請ください。
書式・様式ダウンロード
- 医薬品等の製品販売後調査実施マニュアル(依頼者用) (PDF)
- 【様式7-1】医薬品等の製造販売後調査実施依頼申請書(依頼者用) (Excel)
- 【様式7-2】医薬品等の製造販売後調査実施申請書(医師用) (Excel)
- 【様式7-5】医薬品等の製造販売後調査実施依頼変更届(依頼者用) (Excel)
- 【様式7-6】医薬品等の製造販売後調査委託料支払通知書(依頼者用) ( Excel)
- 【様式7-7】医薬品等の製造販売後調査終了報告書(依頼者用) (Excel)